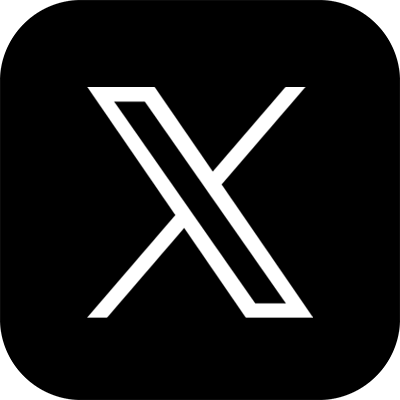院長・酒井直樹が参加してる各種のセミナー
- 日本歯科医師会生涯研修事業 修了証
- インプラントの長期予後に関してのWeb研修
- 休診日ごとに歯科の研鑽を積むための研修
- デジタル歯科の最新知識を学ぶ
- バネの目立たない入れ歯の最新知識を学ぶ
- 保険診療の理解のために【歯科】
- 「か強診」施設基準を満たす介護対応研修会参加
- 和田精密さんの義歯(入れ歯)セミナー受講
- 認知症対応力向上研修会を受講
- 午前は歯科医療安全管理研修会、午後は仙台へ
- 自分の進化を確認出来るデンタルショー
日本歯科医師会生涯研修事業 修了証
確か2年に一度送られて来るんだと記憶してますが、所属する『日本歯科医師会』が主催する生涯研修事業制度ってのがありまして、e-ラーニングでの受講が可能なので時々チェックしていた結果報告として写真の様な修了証が送られて来ます。
考えてみたら歯科医師の免許は一度取得したら一生通用してしまうので、向上心を持って研鑽を重ねない限り自分自身は進化しません。ありがたいことに歯科医師会では各会員を鼓舞する為にこういった制度を充実させてくれてます。
講座受講後には小テストも課せられるので・・・しっかり視聴しないと単位を取得出来ないというニクい仕組みでもあるんです。(汗)
今後も新たな知見を得るためにも幅広く視聴してレベルアップを図って参ります。(2020年8月)

インプラントの長期予後に関してのWeb研修
当院のインプラントは海外大手のジンマー・バイオメット・デンタル社の製品であります。一般の方には『?』な話かとは思うのですが世界的に認められてるメーカーであるということは実は大いに大切な事でもあるんです。
私は2015年以来、一貫してこの会社の製品を使ってるのですが、その間に消えて無くなってしまったインプラント・メーカーは実は多数あります。(泣)
例えばクルマのメーカーを想像してみて下さい。有り得ない話ですが、TOYOTAが5年後に無くなってしまったら部品供給が途絶えるという事になりますので万が一にインプラントのパーツが壊れてしまった際にはどうすることも出来なくなってしまうことが予想されます。

海外大手の製品は我々の仕入れ値も高額です。他方、安売りを前面に押し出してる会社に飛びついてしまい、もしその会社が無くなってしまった際には対応に苦慮されるのは患者さんであります。
大手は、表題のような研修サポート事業がしっかりしてるので歯科医としてもとても助かるのです。今回も学ぶべき点がとても多いありがたいWeb研修でありました。(2020年8月)
休診日ごとに歯科の研鑽を積むための研修
歯科医になってから四半世紀の歳月が流れましたが、他の業界同様この歯科界の技術の進歩・革新は目覚ましいものがあります。
かつて大学歯学部で学んだ常識は非常識であったり、インプラント治療にしても歯科用CTにしてもレーザー治療、CAD/CAM機器セレック治療にしても当時存在さえ「?」だったようなものが現在は当たり前になってきました。
そんな中、歯科医師の頭の中だけが旧態依然としていては我々は仕事になりません。
常に最新の知見を学び、最新の機材を導入し続けるために研鑽を欠かせません。加えて人口減少時代に突入しての人手不足は深刻です。かつて考えもしなかった人的マネージメントの知識も学ばなくてはならなくなりました。昨今はeラーニングの制度が重宝するのですが、どうしても対面での情報収集でないと睡魔に襲われ実が入らない欠点があります。悩ましいところです。
常にこの業界のトップ数%に位置すること…日々考えながら研鑽を重ねる毎日です。
デジタル歯科の最新知識を学ぶ
当院で2013年に導入した「セレック」のシステム、最近はセラミックを用いた審美歯科に関してサイトを立ち上げたりして最新の口腔内スキャナーや付随する最新版ソフトの勉強をしてきました。この「デジタル化」のメリットは…
「デジタル歯科」のメリット!
① 型取りが撮影なのでそれほど苦しくない
② 精度・正確さは比べものにならないほど優れている
③ 医療廃棄物(型取りのグニュッとしたやつ&石膏模型)が出ない
④ デジタルデータなので保管場所すら要らない
⑤ 送信ボタンを押すだけで技工士さんはインターネット経由で瞬時にデータ受信
時代はもう完全に変わったんですね。日進月歩の技術革新に遅れを取らぬよう学んで参りました。(2018年11月)


バネの目立たない入れ歯の最新知識を学ぶ
皆さんは入れ歯にどういったイメージをお持ちでしょうか?
日々、多くの患者さんと接していると「部分入れ歯」と「ブリッジ」の違いさえご存知ない方が多かったりしますが、針金等で他の歯に引っかけて支えている物が「部分入れ歯」です。
そんな「部分入れ歯」も随分進化していて、「バネ」と称される針金が目立たない物になってきました。当院は震災前から導入していたのですが、需要が高まってきたのか新素材や新たな考えが編み出されてきたので、その辺りの最新事情を探ってきました。その際の模様はこちらで取り上げました。(2018年10月)


保険診療の理解のために【歯科】
当たり前ですが、保険診療に従事する医療機関である以上はその内容をしっかり把握し理解してないとなりません。厚労省(国?)が策定したルールに従わなければ保険医に相応しくないと判断されても仕方ないでしょう。ただ、この制度が2年に一度ではあっても結構変わるんです。(泣)
その都度、しっかり制度を理解するための東北厚生局主催の集団指導を受けてきました。これは6年に一度義務づけられています。(2018年10月)

「か強診」施設基準を満たす介護対応研修会参加
当院は、「かかりつけ機能強化型歯科診療所(か強診)」の認定を受けていますが、この施設基準を満たすために各種の研修会に参加し学ばねばなりません。この日は郡山に赴きましたが、診療時に毎回見ていてもどちらかというと注視することの少ない「舌」に関して最新の知見を得て帰ってきました。

多くの方が「舌」の働きに関して「?」の部分が多いと思うのですが、実はとても重要な役割を果たしています。講師の菊谷先生は摂食嚥下の第一人者の方ですが、噛めないことを主訴になさっている多くの方はもしかすると舌の機能不全ではないかと仰います。考えてみたら全身の筋力が衰えて以前は容易くできたことができなくなるのが高齢化でありましょう。舌も例外ではないという視点に立つと見えなかったものが見えてくるような気がします。その際の模様はこちらで取り上げました。(2018年10月)
和田精密さんの義歯(入れ歯)セミナー受講
どれだけインプラントが普及したとしても、欠損補綴と呼ばれる入れ歯やブリッジによる治療法が廃れることはないでしょう。むしろ高齢者の方々が多くなる今後は有病率も相俟って、外科処置が敬遠されて麻酔しないで済む入れ歯治療は欠かせなくなってくるのかもしれません。特に、当院で人気があるバネの見えない(目立たない)入れ歯は今後のトレンドになりましょうか。セミナーで細やかな適合性アップの秘策等も伝授していただけました。その際の模様はこちらで取り上げました。(2018年9月)


認知症対応力向上研修会を受講
私には八十路を越えた親がいますが、ありがたいことに認知症と無縁でいてくれるので現実を理解していないところがあります。昨今は70代の認知症の方が大勢いらっしゃる事を日常の臨床で解っているのですが…。そんな折に地元いわきで表題の「認知症対応力向上研修会」が開催され参加してきました。
歯科から発信する認知症の予兆…ご家族にそれとなく伺ってみることが肝要との話でしたが、事が事だけに迂闊にできない現実に直面する今日この頃です。(2018年9月)
午前は歯科医療安全管理研修会、午後は仙台へ
一年間に日曜日は52週、お盆や年末年始を除外すれば実質50回くらいしかないので、困ったことに有益な講習会が重なる事態に見舞われます。この日は午前中に内郷の保健センターで日々の診療に欠かせない「医療安全管理研修会」を受講。
終了直後に北上して、いつも研鑽を共にしている「東北セレックミーティング」の連中とラミネートベニアという審美修復の最新の知見を学んできました。これが東京と仙台であればダブルヘッダーは不可能ですが、いわきと仙台ならなんとかでした。(汗)
その際の模様はこちらで取り上げました。(2018年9月)

自分の進化を確認出来るデンタルショー
私は基本的には新しいものが大好きで、仕事上の機器も新製品が出るとワクワク感を抑えにくくなる性格です。毎年9月初旬に仙台で東北デンタルショーが開催され、歯学部6年生の長男の顔を見がてら観に行ってきました。目を瞠るほどの進化を遂げている新製品があれば、旧態依然とした雰囲気から脱却できずにいるブースも目立っていました。(汗)
「新しければすべて良い」ではないと思いますが、例えば10年…いや、5年前であってもパソコン&スマホは劇的に進化を遂げている昨今、立ち止まるのはどうかと思った次第です。その際の模様はこちらやこちらで取り上げました。(2018年9月)